負の歴史の伝承シンポジウム 如何に東日本大震災を伝えるか? (Japanese or English translated captions are available)
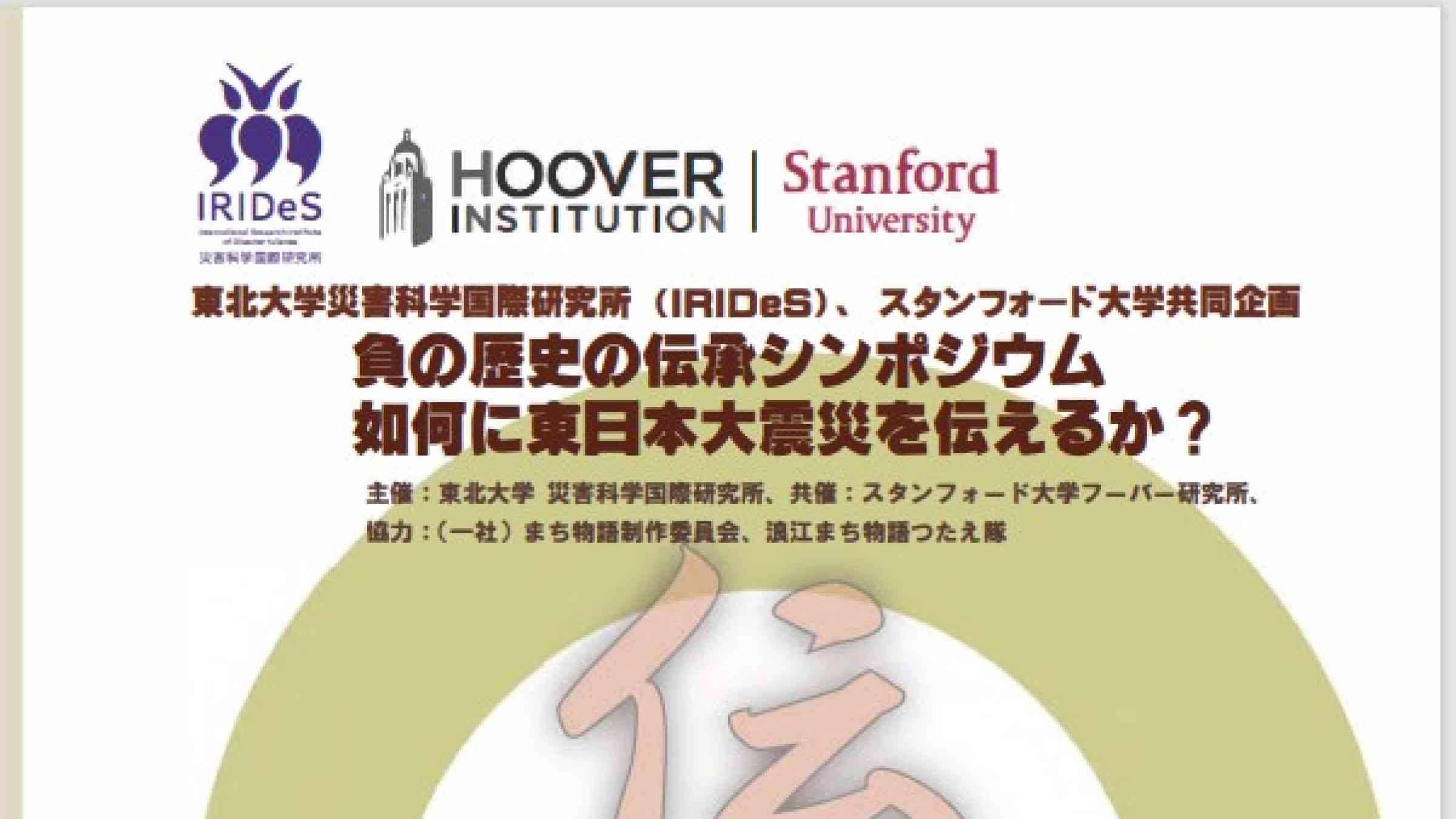
人類史上、負の歴史を継承することは重要ではあるが、それに伴う課題も多々ある。例えば、第二次世界大戦の語り部活動や、広島の原爆ドームのような負の遺産の保存が決まったのも終戦後何十年もかかった。「3.11」という災害の負の歴史の伝える手法の課題も数多くあり、同じような災害が二度と起こらないように東日本大震災の記憶を伝える人もいれば、「震災遺構」となった被害を被った建物をもはや見たくない或いは、語り部の話により大震災のつらい経験を思い出したくない人もいる。同震災は地震・津波といった自然現象による被害だけでなく、原子力発電所の事故という放射能による被害が社会に対し大きな影響をあたえた。東日本大震災と一括りにされがちであるが、津波の被害が大きかった宮城県や岩手県と原子力災害という目に見えないリスクとスティグマを背負った福島県との相違認識も必要である。例えば、前者は語り部が多いものの、後者では語り部が少ないなどの課題がある。当シンポジウムでは、東日本大震災という日本史上でも稀なナショナル・クライシスの記憶、伝承という課題を考察、討議する。その記憶形成、伝承の具体的ツールとして、被災地での紙芝居上演、デジタル・アーカイブスを検証する。
日 時 2023年9月23日(土) 9:00~17:00
開催形式 ハイブリッド(リモートおよび対面)
参加方法 こちらのリンクから事前に登録してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePGWaVGpR6wUGnXhSuwPxElNCo2i2iyKPYrJLgg5I2Ia6J7A/viewform
申込締切 参加登録:2023年9月20日(水)
会 場 東北大学災害科学国際研究所(アクセス地図)
〒980-8572 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1
Tel:022-752-2099(災害文化アーカイブ研究分野)
言 語 日本語あるいは英語
【スケジュール】
開会の挨拶
セッション1:文化的記憶と物で語る
『戦争体験、植民地体験という困難-いかに語られ、いかに継承されてきたか?』
スピーカー1:蘭信三(上智大学、大和大学)
『韻を踏む災害の歴史:足尾銅山と福島第一』
スピーカー2:アンドルー・ゴードン(ハーバード大学)オンライン参加
『悪魔のアーカイブ、又は東京電力のお墓の建て方』
スピーカー3:森本凉(プリンストン大学) オンライン参加
セッション2:記憶の伝承と表現
『我が国における災害語り部活動の現状:災禍を伝える東北とそれ以外の地域に対する分析』
スピーカー4:佐藤翔輔(東北大学災害科学国際研究所)
『語り部とZeitzeugen:歴史の伝承活動』
スピーカー5:アンナ・ヴィーマン(LMU ミュンヘン大学)
『岩手、宮城と福島で見えてくる東日本大震災を語り継ぐ課題』
スピーカー6:ゲルスタ・ユリア (東北大学災害科学国際研究所)
紙芝居と語り部
上演:村上美保子、村上哲夫、福本英伸(まち物語製作委員会)
セッション3:紙芝居の歴史的考察とデジタル・アーカイブス(敬称略)
『プロパガンダ紙芝居』
スピーカー7:山本武利(NPO法人インテリジェンス研究所)
『国民に戦争を売る: プロパガンダ紙芝居のストーリー展開』
スピーカー8:シャラリン・オルバー(ブリチッシュ コロンビア大学) オンライン参加
『紙芝居のデジタル化:グループ消費から個人の経験へ』
スピーカー9:上田薫(スタンフォード大学フーバー研究所)
ディスカッション
閉会の挨拶
【お問い合わせ先】ユリア・ゲルスタ(災害文化アーカイブ研究分野)
メール:gerster@irides.tohoku.ac.jp