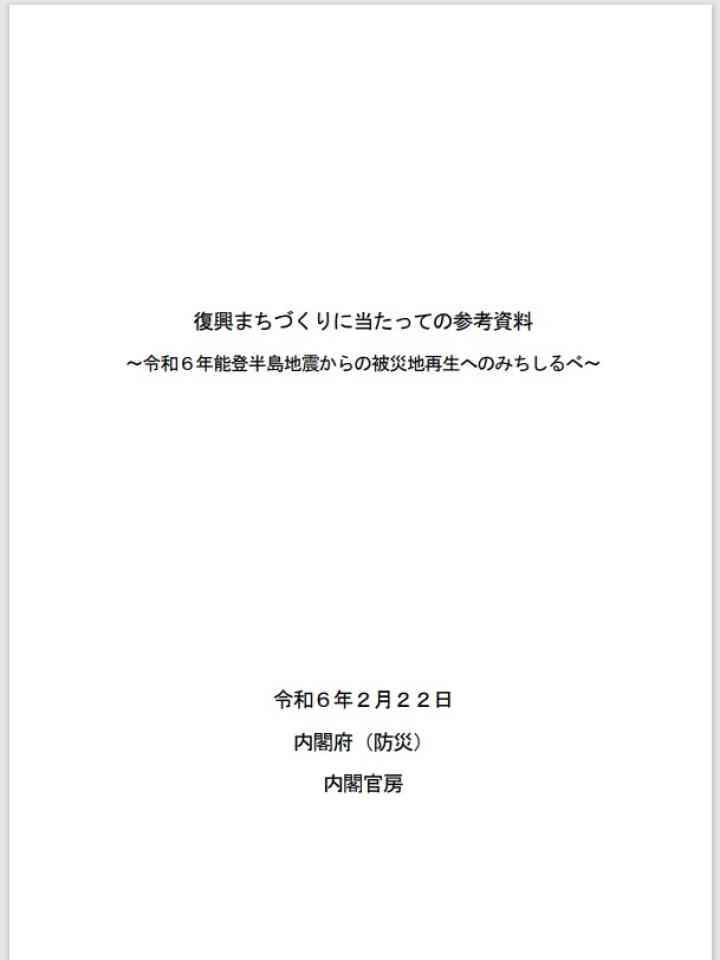復興まちづくりに当たっての参考資料 ~令和6年能登半島地震からの被災地再生へのみちしるべ~
復興まちづくりの検討に当たっては、被災された⽅々が、再び住み慣れた⼟地に戻って来られるよう、そして⼀⽇も早く元の平穏な⽣活を取り戻せるようにすることが何よりも重要です。
復興まちづくりは、地域の将来像を描き、実現していく取組そのものであることから、被災者をはじめとする地域住⺠が地域の将来像を共有し、地域が中⼼となって進めていく必要があります。
このため、検討に当たっては、まず市町村において地域住⺠の意向を丁寧に伺うとともに、まちづくり協議会など地域の意⾒を集約・形成していく場をつくり、それを活⽤してしっかりと議論を重ねることが⼤切です。こうしたプロセスを経て、地域の将来像とその実現⼿法を復興まちづくり計画として取りまとめた上で、その後は、計画に盛り込まれた⼀つ⼀つの事業について合意形成を図りながら進めていくことになります。その際、住⺠の意向は時間の経過とともに変化する可能性があることについても留意する必要があります。
これまでの災害からの復興の経験を踏まえると、地域住⺠が時間をかけて検討するはずであった住まいや 暮らし、⽣業の将来について、災害を契機として、短期間で考え判断していかざるを得なくなり、結果として、⼤災害は、その地域における社会トレンドを加速させるという側⾯があると⾔われています。
特に今回の地震においては、⾼齢化・過疎化の進⾏する半島部の市街地や集落が被災地となったこと、建 物の倒壊だけでなく、⽕災、津波、液状化、海底隆起など多様な被害が広範囲に発⽣したことを踏まえると、被害への対応も地域特性や被害状況に応じた多様なものとする必要があります。このような地域特性や被害状況を考慮しながらも、できるだけ早く地域の将来の姿を⽰すことが重要となります。
具体的には、市町村においては、被災者の住まいを確保する早期の段階から、コミュニティの維持や⽣業の再⽣に⼗分に留意しながら、可能な限り元の住まいの近くでの居住の確保を考えるなど、地域の住⺠⼀⼈⼀⼈が、住まいと暮らしや⽣業についての将来展望を持てるような、まちの姿を⽰していく必要があります。
復興の主体は、住⺠に最も⾝近で地域のことを理解している市町村です。市町村が地域の将来像を描き、 その実現に向けて施策を推進するに当たっては、国は、その実現を後押しするために必要な制度を⽤意するとともに、県とともに技術的な⽀援や⼈的⽀援を⾏っていきます。
復興まちづくりに当たっては、市町村、県、国が相互に協⼒し、それぞれが役割分担しつつ、地域の将来像の実現に向けて、必要な事業を調整し実施していくことが重要です。
こうしたことから、復興まちづくりを円滑に進めるためには、以下の3点を基本的な考え⽅とすることが必要と考えられます。
- 地域住⺠の意向を丁寧に把握し、地域に寄り添った合意形成⼿続きを進めること。
- 住まいと暮らし、⽣業について将来展望を持てる地域の姿を早期に⽰すこと。
- ⾃治体が考える地域の将来像の実現を後押しするため、国は必要な⽀援制度・事業を明⽰し、バックア ップしていくこと。
また、まちの再⽣は、住まいや店舗等の建物と、道路や⽔道等の各種インフラや、⾼齢者施設・学校・⽂化財といった地域の核となる施設などからなる「まちのかたち」と、⽔産業、農林業、伝統産業・観光業等からなる「⼈々の⽣業とまちのにぎわい」が、それぞれうまく組み合わさり整合した形で⾏われることが重要です。
Explore further