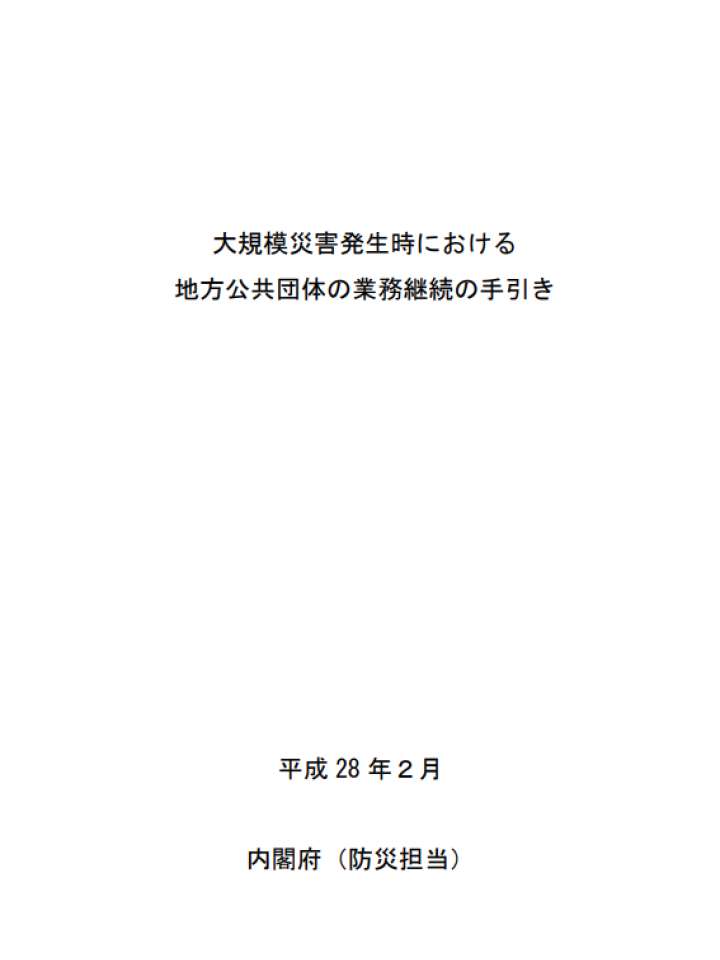地震等による大規模災害が発生した際、地方公共団体は、災害応急対策や災害からの復旧・復興対策の主体として重要な役割を担うことになる一方、災害時であっても継続して行わなければならない通常業務を抱えている。しかしながら、過去の災害では、地方公共団体自身が被災し、庁舎や電気・通信機器の使用不能等により災害時の対応に支障を来たした事例が多数見受けられるところであり、このような非常事態であっても優先的に実施すべき業務を的確に行えるよう、業務継続計画の策定等により、業務継続性を確保しておくことが極めて重要である。そこで、内閣府(防災担当)では、地震発生時の業務継続の検討に必要な事項及び手法等を取りまとめた「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説(第1版)」(平成 22 年4月。以下「旧手引き」という。)を策定し、地方公共団体における業務継続計画の策定促進を図ってきたところである。
しかしながら、平成 23 年3月に発生した東日本大震災は、東日本各地に甚大な被害をもたらし、特に、庁舎・職員が被災した市町村においては、一時的に行政機能が失われる深刻な事態に陥り、その業務の実施は困難を極めるものとなった。このことは、地方公共団体における業務継続計画の策定の必要性をあらためて認識させることとなったが、業務継続計画の策定率は、市町村においては依然として低く、特に人口の少ない小規模な市町村ほど低位な傾向にある。
この要因の1つとして、旧手引きに沿った業務継続計画の策定方法が小規模な市町村にとって作業量が多いものとなっていることが考えられたため、平成 26 年度に有識者等による「地方公共団体の業務継続の手引き改定に関する検討会」において検討を行い、人口が1万人に満たないような小規模市町村であってもあらかじめ策定していただきたい事項をまとめた「市町村のための業務継続計画作成ガイド」(平成 27 年5月。以下「ガイド」という。)を作成した。この「ガイド」は、様式を使用し、その記入例を参考に検討を進めることで、業務継続計画のうち特に重要な要素が定められるように構成しており、業務継続計画を未策定の市町村においては、まずは「ガイド」を参考に検討を進め、業務継続計画を是非とも早期に策定していただきたい。
そして、今般、より実効性の高い業務継続計画の策定を支援することを目的として、旧手引きについても、東日本大震災の教訓や近年の災害事例等を踏まえ内容の拡充等を図り、「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」(以下「手引き」という。)として改定することとした。業務継続計画を作成する際には、「ガイド」のほか必要に応じて本「手引き」も参照し、各地方公共団体の実情に即して項目を適宜追加するなどさらに充実した内容としていたただきたい。
Explore further