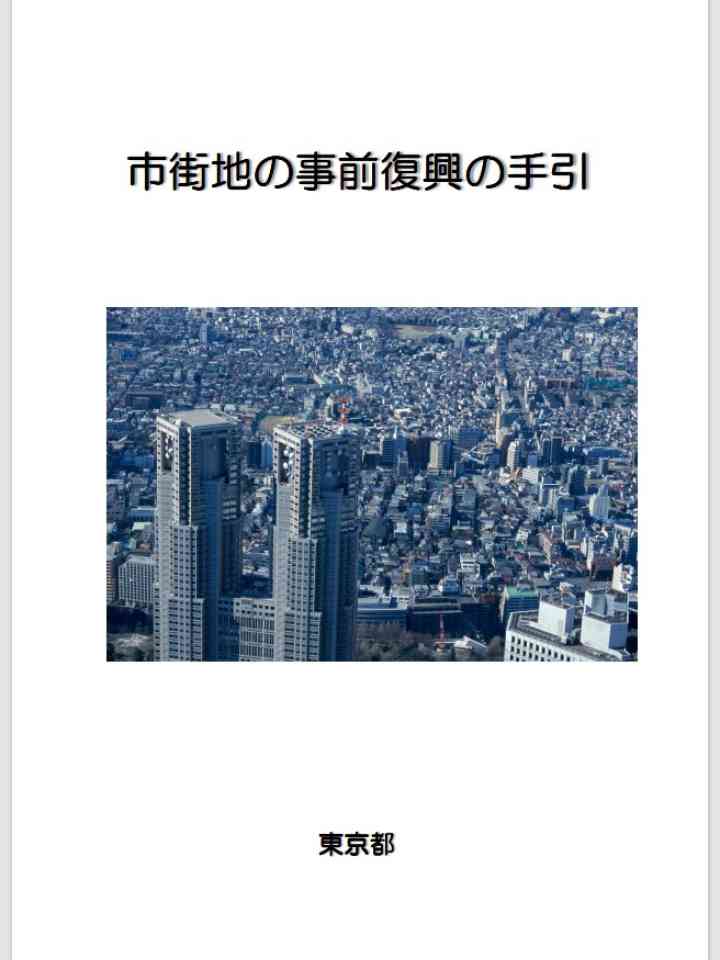首都直下を震源とするM7クラスの地震が 30 年以内に起きる確率は 70%程度と推定されている。東京都(以下「都」という。)では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、被害の軽減を目的とした「防災都市づくり」や、震災復興マニュアルの策定、都市復興模擬訓練の実施など、迅速な都市の復興に向けた事前の取組を鋭意進めているが、こうした取組が完成する前に大地震が発生することも危惧される。
大震災の被災時に、応急対応や復旧を行いながら、復興まちづくり計画案の作成、復興に向けた合意形成、時限的市街地の検討などを短期間に進めることは行政、住民等にとって大きな負担となる。このため、大地震が起きた際の備えとして、備蓄物資を用意するのと同様に、市街地の復興に向けた準備として、地域における事前復興の取組をあらかじめ進めておくことが必要である。
震災に向けた事前の取組としては、被害の軽減を目指す「防災都市づくり」と、被災後の復興に向けた課題解決に要する負担を軽減する「事前復興」の取組があり、この2つの取組を併せて進めることが重要である。
「防災都市づくり」は、建築物の不燃化や耐震化、道路等の都市基盤整備を進め、市街地の安全性の向上を図り、震災に強いまちとすることであり、被害そのものを減少することにより復興に要する負担の軽減、時間の短縮を図るものである。
「事前復興」の取組は、事前に行うことが可能な対応策を講じておくことにより、復興時の課題解決に要する負担軽減や復興まちづくりに関する合意形成の円滑化を図るものである。具体的には、復興計画の検討に必要な条件整理や復興の将来像・目標像の検討、訓練の実施による復興業務を迅速に進められる人材育成や体制づくり等の取組が挙げられる。
平常時に進めている「防災都市づくり」の実践と併せて「事前復興」の取組を進めることにより、復興のスピードが確保されるとともに、より良い復興が実現できる。また、防災都市づくりの延長上に復興があるという見方もできることから、「防災都市づくり」と「事前復興」の取組は密接な関係があり、平常時からコミュニティ活動等の中で、並行して取り組んでいくことが有効である。
Explore further