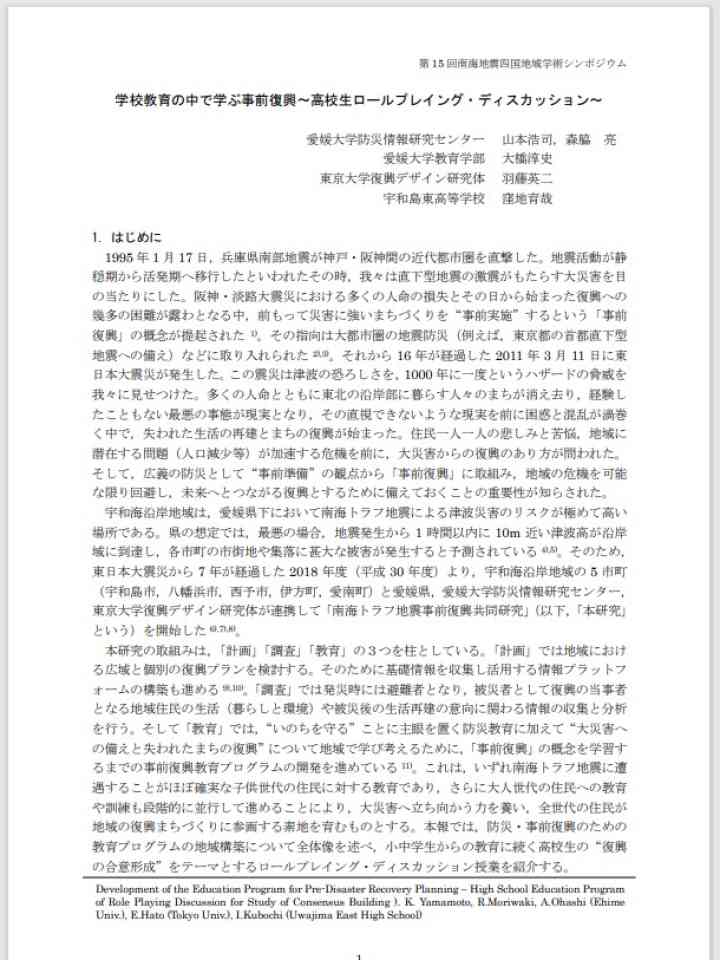学校教育の中で学ぶ事前復興~高校生ロールプレイング・ディスカッション~
1995 年 1 月 17 日、兵庫県南部地震が神戸・阪神間の近代都市圏を直撃した。地震活動が静穏期から活発期へ移行したといわれたその時、我々は直下型地震の激震がもたらす大災害を目の当たりにした。阪神・淡路大震災における多くの人命の損失とその日から始まった復興への幾多の困難が露わとなる中、前もって災害に強いまちづくりを“事前実施”するという「事前復興」の概念が提起された 。
その指向は大都市圏の地震防災(例えば、東京都の首都直下型地震への備え)などに取り入れられた。それから 16 年が経過した 2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生した。この震災は津波の恐ろしさを、1000 年に一度というハザードの脅威を我々に見せつけた。多くの人命とともに東北の沿岸部に暮らす人々のまちが消え去り、経験したこともない最悪の事態が現実となり、その直視できないような現実を前に困惑と混乱が渦巻く中で、失われた生活の再建とまちの復興が始まった。住民一人一人の悲しみと苦悩、地域に潜在する問題(人口減少等)が加速する危機を前に、大災害からの復興のあり方が問われた。そして、広義の防災として“事前準備”の観点から「事前復興」に取組み、地域の危機を可能な限り回避し、未来へとつながる復興とするために備えておくことの重要性が知らされた。
本研究の取組みは、「計画」「調査」「教育」の3つを柱としている。「計画」では地域におけ る広域と個別の復興プランを検討する。そのために基礎情報を収集し活用する情報プラットフォームの構築も進める。「調査」では発災時には避難者となり、被災者として復興の当事者となる地域住民の生活(暮らしと環境)や被災後の生活再建の意向に関わる情報の収集と分析を行う。そして「教育」では、“いのちを守る”ことに主眼を置く防災教育に加えて“大災害への備えと失われたまちの復興”について地域で学び考えるために、「事前復興」の概念を学習するまでの事前復興教育プログラムの開発を進めている。これは、いずれ南海トラフ地震に遭遇することがほぼ確実な子供世代の住民に対する教育であり、さらに大人世代の住民への教育や訓練も段階的に並行して進めることにより、大災害へ立ち向かう力を養い、全世代の住民が地域の復興まちづくりに参画する素地を育むものとする。
Explore further