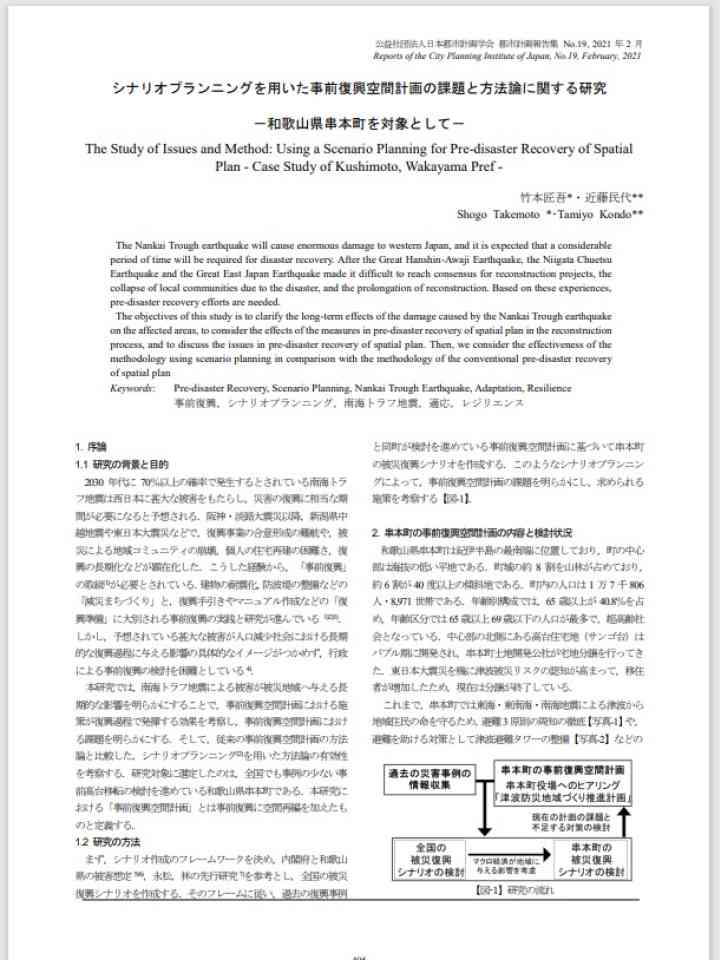シナリオプランニングを用いた事前復興空間計画の課題と方法論に関する研究 -和歌山県串本町を対象として-
2030年代に70%以上の確率で発生するとされている南海トラフ地震は西日本に甚大な被害をもたらし、災害の復興に相当な期間が必要になると予想される。阪神・淡路大震災以降、新潟県中越地震や東日本大震災などで、復興事業の合意形成の難航や、被災による地域コミュニティの崩壊、個人の住宅再建の困難さ、復興の長期化などが顕在化した。こうした経験から、「事前復興」の取組が必要とされている。
建物の耐震化、防波堤の整備などの「減災まちづくり」と、復興手引きやマニュアル作成などの「復興準備」に大別される事前復興の実践と研究が進んでいる。しかし、予想されている甚大な被害が人口減少社会における長期的な復興過程に与える影響の具体的なイメージがつかめず、行政による事前復興の検討を困難としている。
本研究では、南海トラフ地震による被害が被災地域へ与える長期的な影響を明らかにすることで、事前復興空間計画における施策が復興過程で発揮する効果を考察し、事前復興空間計画における課題を明らかにする。そして、従来の事前復興空間計画の方法論と比較した、シナリオプランニングを用いた方法論の有効性を考察する。研究対象に選定したのは、全国でも事例の少ない事前高台移転の検討を進めている和歌山県串本町である。本研究における「事前復興空間計画」とは事前復興に空間再編を加えたものと定義する。
Explore further