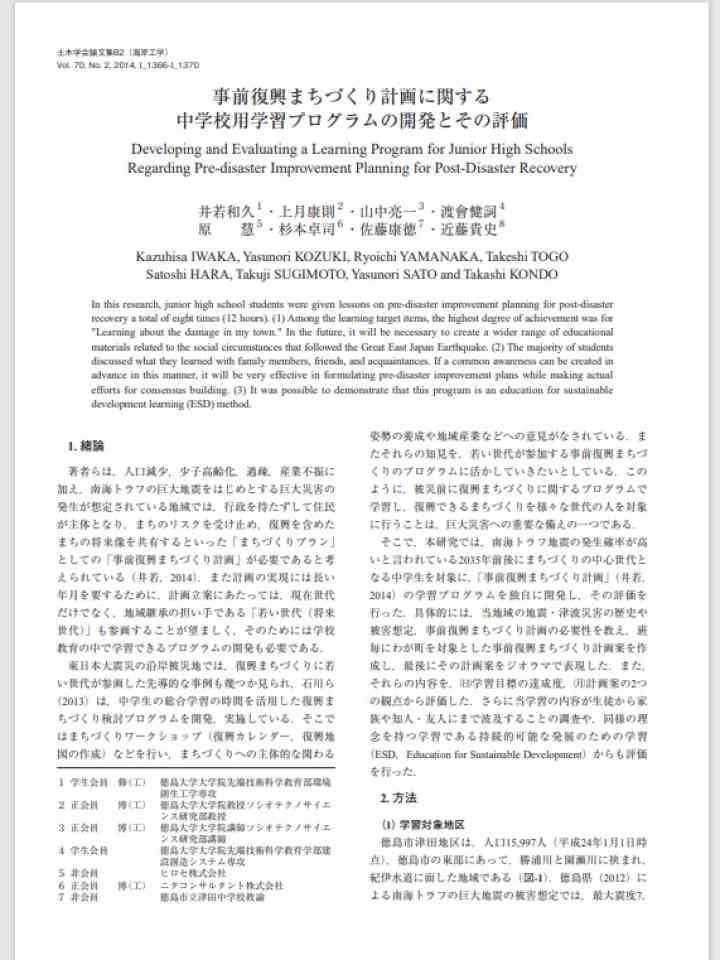事前復興まちづくり計画に関する中学校用学習プログラムの開発とその評価
人口減少、少子高齢化、過疎、産業不振に 加え、南海トラフの巨大地震をはじめとする巨大災害の発生が想定されている地域では、行政を待たずして住民が主体となり、まちのリスクを受け止め、復興を含めたまちの将来像を共有するといった「まちづくりプラン」 としての「事前復興まちづくり計画」が必要である。また計画の実現には長い年月を要するために、計画立案にあたっては、現在世代だけでなく、地域継承の担い手である「若い世代(将来世代)」も参画することが望ましく、そのためには学校教育の中で学習できるプログラムの開発も必要である。
東日本大震災の沿岸被災地では、復興まちづくりに若 い世代が参画した先導的な事例も幾つか見られる。そこではまちづくりワークショップ(復興カレンダー、復興地図の作成)などを行い、まちづくりへの主体的な関わる姿勢の養成や地域産業などへの意見がなされている。またそれらの知見を、若い世代が参加する事前復興まちづくりのプログラムに活かしていきたいとしている。
このように、被災前に復興まちづくりに関するプログラムで学習し、復興できるまちづくりを様々な世代の人を対象に行うことは、巨大災害への重要な備えの一つである。そこで、本研究では、南海トラフ地震の発生確率が高いと言われている2035年前後にまちづくりの中心世代となる中学生を対象に、「事前復興まちづくり計画」の学習プログラムを独自に開発し、その評価を行った。具体的には、当地域の地震・津波災害の歴史や 被害想定、事前復興まちづくり計画の必要性を教え、班毎にわが町を対象とした事前復興まちづくり計画案を作成し、最後にその計画案をジオラマで表現した。また、それらの内容を、(1)学習目標の達成度、(2)計画案の2つ の観点から評価した。さらに当学習の内容が生徒から家族や知人・友人にまで波及することの調査や、同様の理念を持つ学習である持続的可能な発展のための学習(ESD、Education for Sustainable Development)からも評価 を行った。
Explore further